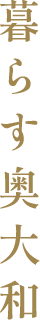 Try Living in Okuyamato.
Try Living in Okuyamato.
Organized by Nara Pref.
Organized by Nara Pref.
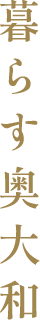

文=岩城良平(ねこのて舎) 写真=村上由希映
2025年1月18日。昨年末から続いた寒さが嘘のような、柔らかな日差しと陽気に包まれた良き午後。生駒から一組の若い夫婦が上北山村を訪れました。二人そろって「釣り」が趣味という、自然が大好きな守崎夫妻です。

小谷さん:ようこそー! お久しぶり!!
道の駅で出迎えたのは、ホストの久米恭子さんと小谷雅美さん。ともに移住者の二人は”苔と暮らしを考える”ユニット「mossumo」として、空き家活用や移住支援など様々な活動に取り組んでいます。大阪で開かれた県主催の移住フェアで出会ったお二人とはすでに顔見知りで、親しげな挨拶が交わされます。

馴れ初めのきっかけも釣りだったという守崎夫妻。「いつかは」と心に抱き続けている自然豊かな土地への移住を、よりリアルに感じ、考える機会にしたいと今回の「暮らす奥大和」に参加してくれました。
「大台ヶ原」で知られる奥深い山々と幾重にも流れる美しい川、そして青く晴れ渡った空。今日のお天気は、まるで上北山の大自然が満面の笑顔で、人生の新たな道を模索する二人を歓迎してくれているようです。
一行がまず向かったのは、滞在の拠点となる「ことちのいえ」。上北山村を構成する4つの地区(西原・河合・小橡・白川)のうちの一つ、小橡集落にある移住体験住宅です。

この施設の管理を委託されている久米さんが、丁寧に案内・説明をしてくれます。地域の伝統的な「田の字造り」の間取りはそのままに、心地よく設え直された広いキッチンやお風呂。Wi-fiも完備して、ひとときの田舎暮らしを味わうには十分すぎるほど。

建築事務所に勤め、古い建物が大好きだというみさきさんは大喜び。勝手口を出るとすぐそこに川原という立地も、二人にとって理想のイメージそのままだったようです。入居の手続きを一通り終えた後、まずはその川原に行ってみることになりました。

小橡地区を流れるこの小橡川は、村内でも屈指の清流。普段登山ガイドを生業の一つとしている小谷さんが、上北山の川の魅力や楽しみ方を語ってくれました。興味深く話に耳を傾ける夫妻。とりわけここまで物静かだった周蔵さんの言葉数が、この川に着いてから明らかに増えたのがわかります。会話の間もついつい川に目配せし、魚の影を追ってしまう周蔵さん。本当に魚が好きだという人柄が伺えます。

続いて、お向かいの奥村さんにご挨拶。「どうぞごゆっくり」と応じてくださる温かい笑顔から、ホストの二人と地域の方たちとの確かな信頼関係が感じられます。ゲストの紹介を終え、世間話をしたら、次は車で小橡集落を回ってみることに。

訪ねたのは、小橡集落でものづくりの仕事を営む中本さん親子。まずはFRPという素材の加工業を営む、息子・和秀さんの工房にお邪魔します。
小谷さん:わ、かっこいいー!
バイクや車のカバーのようなパーツと型金、見慣れぬ道具や材料が整然と並ぶ室内に踏み入れるやいなや、感嘆の声が上がります。「私たちもここに入るのははじめて!」と、ホスト二人もちょっと興奮気味。

和秀さん:型がメーカーから届いて、ここでそれを量産するという感じですね。型にカーボン生地を貼っていって、FRPで厚みをもたせて、その上に何種類も樹脂を使い分けて塗って。一枚ものではできないんでね、継いでいって。
実際の商品を見せながら、ご自身の仕事についてわかりやすく説明してくれる和秀さん。

仕事の醍醐味や始めたきっかけ、地域で仕事をすることのメリット・デメリット。「移住先での仕事」が一つの課題でもある守崎夫妻にとって参考になりそうなお話も伺いながら、大人の社会見学とでもいうようなわくわくした時間が流れていきます。
外から何かを削るような甲高い音が聞こえてきました。同じ敷地内、隣の建屋の軒先で木材をプレーナーにかけていたのは、和秀さんの父・中本貞司さん。

貞司さんは木工職人。役場を退職後に働いた製材所での経験をきっかけに、「けやき工房なかもと」を20年ほど前に立ち上げました。村のシンボルツリーである欅(けやき)をはじめ、地元産の木材を使った製品を、製材から仕上げの塗装まで一貫して行い製作しています。当初はオーダーメイドの家具が中心でしたが、現在は名刺入れや箸入れなどの小物が売れ筋。新商品の腕時計ホルダーも、道の駅や物産展などで人気を呼んでいるそう。
久米さん:中本さんの作品は本当に緻密なんです。今、村内のあちこちに上北山の木を使ったベンチを設置するプロジェクトをやっていて、その製作もお願いしているんですよ。
と久米さんも、その仕事の確かさに太鼓判を押します。

みさきさん:一から全部、塗装まで? すごい……。お一人でやられているんですか?
古民家だけでなく、木という素材そのものに興味があるというみさきさんが積極的に質問を投げかけます。地域おこし協力隊として半年前に弟子入りした女性ががんばっていると聞き、胸を高鳴らせているような、活き活きとした表情が印象的でした。
作業場を出て、貞司さんのもう一つの“仕事場”へ。

車を少し走らせ到着したのは、同じ集落内にある製材所。林業の衰退に伴い稼働を止め20年ほど経っていたこの施設が、村営のかたちで再稼働されたのが5年ほど前。もともと製材所勤務の経験があった貞司さんは村からの委託を受け、ご自身のものづくりの傍ら、この施設の製材作業を担っています。

木の見方やその性質に合わせた仕事のコツなど、なかなか聞くことのできない興味深いお話が貞司さんから語られます。また、現在の林業そのものの仕組みや後継者の育成といった重い課題についても、率直に伝えてくださいました。
中でも一番驚かされたのは、この製材所でつくった上北山の丸太が、来たる大阪万博のヨルダン館に使われている(!)というお話です。きっかけは、先ほど作業場での久米さんの話にもあったベンチプロジェクト。ベンチのデザインで参加していた、早稲田大学建築学科チームの中にいたヨルダン人学生がその後、万博会場での母国のパビリオン建設にも関わることになり「大好きな上北山の木を使いたい!」と視察チームを村に連れてきてくれたそう。
貞司さん:村のみんなで見に行かんとあかんね。
冗談半分、本気半分のようなその一言には、まるで甲子園に出場する我が村の子どもたちを村総出で応援に行くような、地域ならではの一体感が感じられました。
貞司さんに別れを告げ、車に乗り込むと「次はレトロ建築を見に行きましょう」という久米さん。やってきたのは「小橡自治会館」です。

昭和4年、当時の地域住民による団体組織の拠点として建てられた、築約100年の歴史ある建物。西欧的なモダンさと日本の建築美が混在する、その時代だからこその愛らしい佇まいは、木造校舎巡りをするほど昭和レトロ好きなみさきさんにとって、直球どストライクだったよう。

異国の教会に来たような荘厳ささえ感じる階段を上ると、白と水色を基調とした空間に磨りガラスごしの柔らかい光が美しいメインホールが。さらには、何か映画のセットのような渡り廊下伝いのトイレ。タイムスリップしたような光景の連続に、「すごーい!すごーい!」と興奮の声が止みません。

長い間、年に一度の会議くらいにしか使われていなかった2階のホールでしたが、昨年末には村在住の若手写真家の作品展を、皆で協力して開催したのだそう。地元の木材で地元の職人さんが製作した額縁を使った作品が並び、夜の宴会も大賑わいだったとか。
ご近所の梅屋さんにお話を伺うと、かつての小橡自治会はたいへん裕福で、区内の家の子どもが進学の折には奨学金を発行し、地域一丸「頑張ってこいよ」という気持ちで送り出していたそう。

時代は移り変わっても、また新たなかたちで人々の結びつきの縁になる場所。自治会館はこれからも末長く、そんな役目を果たしていくのかもしれません。

自治会館から集落内を少し歩いていくと、昔ながらの佇まいの商店が現れました。

ここは「先ほど出会った梅屋さんが営む梅屋商店」。日曜を除く週6日営業している、村内での貴重な買い物場所の一つです。
小谷さん:月曜と金曜は熊野から仕入れたお魚やお肉が並ぶ日で、わんさか人が集まるんですよ。

「こんな山の中で新鮮な魚が手に入るなんて!」と驚きの表情を見せるみさきさん。周蔵さんも「トンボシビは、多分ビンチョウマグロのことかな」などと呟きながら、貼り出された仕入れの予定表を興味深げに見つめています。

ホスト二人のおすすめで、皆が揃って購入したのは熊野産のポンカン(本当に甘くておいしかったです!)。こんなの見たことない~と、街ではなかなか見かけないマニアックなお菓子の数々も大人気。

レジのお母さんが「初めてだから、サービスね」と小銭分をおまけしてくれました。幼い頃、親に頼まれお金を握りしめて行った近所のお店。どきどきわくわくしながら大人の世界を覗き込んだ、そんな懐かしい記憶を思い起こさせてくれるような場所が、今も上北山村にはあるのです。


日暮れまでの残り時間、小橡の集落内を散策して過ごすことになりました。銘銘、商店で買ったポンカンやお菓子をぶら下げながら、どこか心懐かしい集落の風景の中を進みます。
「こういう中の小道とか歩くのもまた楽しくて」と久米さん。「あ、マチュピチュ行ってみる?」と小谷さんが応じます。
マチュピチュ?

不思議なやりとりをする二人に導かれ、斜面に立ち並ぶ民家の脇道を上がって行くと、高台の拓けた場所に出ました。二人が「マチュピチュ」と呼ぶ、石垣で段々に区分けされたこの風景は、かつては民家が立っていたのか、はたまた畑だったのか。でもたしかに、どこか異国の秘境の遺跡のような雰囲気。

川沿いに広がる小橡集落と、対岸にそびえ立つ緑の壁のような山林を望む、遥かな光景を見下ろしながら暫しの休憩。記念写真を撮ったり、和やかに談笑をして過ごします。


その足で、マチュピチュからも見えた川沿いのお寺「瀧川寺」にやって来ました。
天皇家が二つに分かれ争った南北朝時代、南朝方の若き天皇「北山宮」が追っ手から逃れるため隠れ住んだのがこのお寺なのだそう。敷地内にある北山宮のお墓は、宮内庁が管理するほど大切に守られているものだと久米さんが解説してくれました。歴史好きにはたまらない由緒ある場所ですが、訪ねた目的がもうひとつ。境内にひと月前に設置されたという、中本貞司さん作のベンチです。

幅や長さの異なる木板が円形に並べられ、座禅ができるよう座面も幅広めにとられています。円が一部欠けているのは、完璧な円(=悟り)をめざして修行するという禅の思想によるもの。
座って目を閉じると、川のせせらぎに時折鳥の声、微かな生活音だけが響く、穏やかで静かな時間が流れます。実は、ここ以外にも村内に少しづつ増えつつあるベンチ。「いずれは100カ所に設置したい」とプロジェクトの目標を語る久米さんに一同大賛成。自分たちが欲しいものを、自分たちの手で一つずつ増やしてゆく。そんな豊かさを味わって、この日は解散。守崎夫妻も体験住宅に戻り、ローカルステイ1日目は終了となりました。
昨日に引き続き、空も山も穏やかに微笑んだ2日目の朝。「ことちのいえ」から顔を出した守崎夫妻は清々しい表情。
みさきさん:本当に静かで。よく眠れました~。
周蔵さん:朝釣りもしましたよ。
聞けば昨日、梅屋商店での買い物の際に、釣り餌になりそうなソーセージをゲットしていたそう。残念ながら釣果はボウズだったようですが、さっそく川を楽しんでいる夫妻の釣り談義にホスト二人も嬉しそうに加わります。

目的地へと向かう車内では、久米さんがさまざまな話を楽しく聞かせてくれます。
村ゆかりの有名人といえば、お笑い芸人「ロッチ」の中岡さんだという話。その親戚の方が村では生き字引のような歴史博士なのだという話。まるで家族や親戚の話をするように、地域への愛情いっぱいの久米さんの話は尽きることがありません。昨年この「暮らす奥大和」をきっかけに移住した、猟師志望の若い男の子の近況。彼が本業とは別に、調理の経験を活かし、ホテルの厨房のスタッフとしても働いているという話から、二人がこの村で働くことのさまざまな可能性へと話題は広がっていきました。
上北山村のアユは、昨年も全国の品評会で賞をもらうほど味が良いが、村内で食べれる所はほとんどなく、また村外に向け販売している人もほとんどいないこと。たとえば誰か、道の駅で塩焼きを焼いて販売したりしないかなーとみんな話しているが、まだやる人がいないこと。そんな話を聞いていると、それ一本で生活していくのは難しくとも、何か守崎夫妻がカチッとはまることのできる、そんな隙間がまだまだこの上北山村にはありそうです。
そんなこんなの話をしながら、やってきたのは、村の南部に位置する「池原ダム湖」でした。雄大な山並みを背景に、眼下に広がる一面のエメラルドブルー。県内外から訪れた釣り客たちのトレーラー車が並ぶボートの昇降場で、「Y企画」の金山耕士さんが出迎えてくれました。

金山さん:卒業して一回関東へ行って、帰ってきて20年くらいですかね。半年で逃げてきました。人混みが嫌で。電車に乗って真冬に汗だくになって、こらあかんわ思て。

大らかな笑顔で経歴を語ってくれる金山さん。上北山村には金山さんのように一度村外へ出ても、やはりここが好きだからと帰ってくる人たちが少なくありません。
金山さん:なんもない所だけど、いい所ですよ。
謙遜する言葉の中にも、ふるさとへの思いがいっぱいに詰まっているのを感じます。

貯水池での釣りが許可されているのは、基本日の出から日没まで。ひとときでも長く楽しみたいという朝の早い釣り客に合わせ、冬場は6時45分、夏場はなんと4時頃にはここで待機しているのだそう。日の出とともに湖にくり出すお客さんを送り出したら、もう一つの家業である土木の事務作業を行いつつ、戻ったお客さんからのボートの引き上げ依頼の電話を待つ、そんな二刀流の毎日。釣りがやりたくてむずむずしてこないのか伺うと、「まったくしないんです。竿もルアーも持ってないです」と金山さん。
意外な答えにびっくりの一同に「バス釣りの話やったら僕じゃなくて、この人。業界ではめちゃ有名な人なんですよ」と紹介してくれたのが、ボートのメンテナンスをされていた安村義樹さん。元々はお客さんとしてY企画に通っていたところ、機械やエンジンの知識を買われ、今では週末スタッフとして働かれているそう。

安村さん:ここはバス釣りの聖地って昔から言われている有名なところなんでね。連休になったら、ほんまに全国から目の色変えて人がやってくる。そんなところ、全国でも琵琶湖かここかくらいですね。僕も小学校の時から、ここに来たくて来たくて。ほんま夢に出てくるくらい。そんな風に思っている釣り好きの子は、僕の世代には多かったと思いますね。
広いダム湖の中には、まるで中国の仙境を思わせる幻想的な絶景を見せてくれるエリアもあるのだそう。お話を聞き終え出発のとき、守崎夫妻にもお礼の言葉を告げる久米さんの姿がありました。
久米さん:二人が来てくれたから、普段は聞かないようなお話を聞くことができる。ありがとう。
ホストの二人にとっても、これまで知り得なかった地域の新たな一面を発見できた、とても大切なひとときとなったようです。

車に乗り込み、続いては白川地区へ。

今回初めて足を踏み入れる、村の一番南に位置するエリアです。かつてダムの建設のため、高台に移転したこの集落は、村の中でも日当たり良く、風も穏やかで「いつもあったかい」土地柄だそう。久米さんの説明通りのぽかぽかした日の光を浴びながら、この集落に最近整備された「移住者用賃貸住宅」へ向かいます。

集落の一斉転居という歴史を反映して、年代としては比較的新しく、状態の良い古民家が整然と並ぶ白川地区。その空き家の一つを村が改修した移住者用賃貸住宅は、元の建築を活かしながらもリフォームの行き届いた好物件でした。

古民家らしい趣を残した居住スペースに、タイルの可愛いお風呂。まるでカフェの厨房のような、土間を活かしたキッチンスペース。勝手口を開けば、ちょっとした自家菜園くらいならやれそうなお庭もあります。

「私のおすすめポイントはね、この小石柄のガラスが、本当に可愛いと思って」と、きらきらした表情で案内する久米さん。「本当に素敵!」とみさきさんとの話に華が咲きます。
みさきさん:どうしても空き家バンクで見つけて、自分で改修して、っていうイメージが強かったんですけど。こんな形もあるんですね。
久米さんと共にこの物件の片付けや提案にも関わった小谷さんが、地域での物件探しについて、アドバイスや思うところを語ってくれました。

移住希望者にとって、右も左もわからない土地にいきなりポンと家を一軒買うというのは、賭けのようなもの。慎重な守崎夫妻のように、そこで思い止まってしまう人々がいるのも頷けます。「もし上北山に来られるときはサポートしますんで」「全力で!」というホスト二人の言葉に、「心強いー!」と喜ぶみさきさん。移住者と住民のそのどちらにもできるだけストレスのないよう、緩やかにご縁をつないでいく、上北山村の施策のあり方はとても丁寧で、他地域にとっても大いに参考になるものだと感じました。




若い子育て世代のお母さんのお話も伺うことができました。
夫婦とも移住者で、上北山村に来て10年以上という島津江直子さん。住み始めた当時よりも少しずつ子どもの数が増えていること、小中学校と保育園があり、スクールバスで送迎してくれることなど、村の子育て事情について教えてくださいました。地域の方たちみんなが、実のおじいちゃんおばあちゃんのように子どもたちを可愛がってくれて、本当に安心感があるのだそう。
忙しい子育ての中でも、村民団体「がんばろらえ!かみきた」のメンバーとしてマルシェを開催したり、手芸品をいろいろ展開したりと、充実した日々を楽しんでいる様子。「この村での子育てってどうですか?」などと聞かずとも、彼女の満面の笑顔がその答えを雄弁に語っているようでした。


白川地区を出て、お昼ご飯の買い物に、地元の歴史ある柿の葉寿司店「ゐざさ中谷本舗」に立ち寄ります。

手馴れた様子で接客してくれた店員さんも、もとは東京からの移住者だそう。

小春日のような暖かさの中、「ことちのいえ」の縁側をお借りしてランチタイム。守崎夫妻が選んでいたのは、小橡にある地区の名前「木和田」と名付けられたお寿司のセット。鯖の柿の葉寿司や鮭のゐざさ寿司、鯛を桜の葉の包み込んだ桜寿司、山菜巻きが詰め合わされていました。

山のお寿司を堪能したら、西原地区に向かいます。

やってきたのは、アマゴの養魚場。新谷卓也さんが出迎えてくれました。
54年前、村と国の共同事業として立ち上がったこの養魚場をお父さんから受け継いだ新谷さん。育てたアマゴはご自身が経営する渓流釣り堀に放すほか、各地の釣り堀や河川放流する事業者に出荷しています。

簡単に「養殖」といっても、産卵から出荷できるまで2年かかるということ。餌代など先行投資も必要だということなど、仕事の厳しさを包み隠さず語ってくださいます。もしかして養殖の仕事に関われる可能性など、魚好きの周蔵さんに合うかもしれないと少し期待しながらの訪問でしたが、現実はそんなに甘いものではありませんでした。

新谷さん:人を雇うとか、施設の拡大とか、そんな余裕はまったくないです。そもそも山から引いてこられる水の量で、育てられるアマゴの量が決まるんです。
確かに、このプールに掛け流されているのは上北山の山からの水。その水の量が育てられる最大値を決めるというお話には、目から鱗がこぼれる思いがしました。

災害対策といって大規模な砂防を造ったり、奥山の木々を伐採してしまうことが、山の保水力を減らし、流れを変えてしまうのだと表情を曇らせる新谷さん。

ふと、プールの周りに張り巡らされた電柵が気になり、どんな動物が悪さをしにやってくるのか伺ったところ、
新谷さん:クマです。
という衝撃的な言葉が。
以前は、クマのクの字もなかったという養魚場に頻繁に下りてくるようになったのが7年ほど前のこと。山はこんなところにも、その環境の変化を告げているのかもしれません。

養魚場から歩いて数分。今度は、この西原地区に昨年新しく移り住んだ、移住者の先輩を訪ねます。お話を伺ったのは、山形県から家族で一年間かけて様々な場所を見て歩き、この土地への移住を決めたという近野聖菜さん。

お子さんの進学を機に家族での移住を思い立ち、新潟、岩手、長野、三重などを巡ったという近野さん。「ここが良さそう!」と思ったら、まずは地図で周辺の地理や自然環境、交通情報までをしらみつぶしにチェックしていったのだとか。もちろん子育ての条件や市町村の移住者支援などの情報も念頭に入れながらも、最後の決め手は、「ここいいなあ」という感覚だったそうです。
近野さん:(上北山村での暮らしを)めっちゃ気に入ってる。ここにして、良かったなーって。上北山はどこか東北に似てるのよ。福島と山形の県境に。前にお父さんを連れてきたら、お父さんも「なんかここ、いいな、ここ福島か」って言って。後でわかったんだけど、大台ヶ原は関西と東北の植生が混じり合って群生してるらしくて。「あ、道理で!」って興奮したよね。

実は、福島県出身のみさきさんとは、住んでいた場所が近かった事実も判明。そんな二人が、この「東北に似てる」上北山村で出会ったことには、ご縁を感じました。
住むところを選ぶときにはまず「安全か」という基準をもつこと。いろんな地域を見て、そこで自分が何をしたいのか、それを出発点に地域を見定めること。先輩からの数々のアドバイスには、みさきさんの心にすっと沁み込むものがあったようです。「楽しみながら夫婦でいろんなところ行ってみて、その中で緩やかに考えるのもいいのかもね」と久米さん。近野さんが応えます。
近野さん:そうそう。そしたらご縁でね、ああ、ここ好きだなあ、この人好きだなって思ったら、そこに行けばいいんだから。
近野さんに別れを告げ、道すがら、最近引っ越したという久米さんの新居にちょっとお邪魔させていただきました。

玄関先では、村役場で働く夫の毅さんが、お休みの今日も壁の改修作業の真っ最中。これまで公営住宅に暮らし、自分たちに合う物件を探し続けていたという久米さんご夫婦。見つけた時は畳もぼこぼこで真っ暗だったという空き家を購入後、最低限のところは大工さんに直してもらい、あとは夫婦で少しずつ改修していく日々を楽しんでいます。

「まだまだ直さないといけないところだらけなんだけどね」と謙遜する久米さんですが、窓の外に清流を望み、斜め天井が隠れ家のような書斎スペース、すっきりと洗練されたキッチンなど、素敵な空間に一同ほれぼれとしてしまいました。
おくどさんを使えるようにしたり、薪ストーブを設置したり、まだまだやりたいことはいっぱい。ゆっくりと自分たちのペースで、暮らしながら家をアレンジしていく。創意工夫の日々がこれからも続いていきそうな久米さんのお家を見学しながら、守崎夫妻も理想の住まいのイメージを膨らませているようでした。

続いて、「釣り好きの周蔵さんにぜひ会ってほしい」と訪れたのは、秘密基地を思わせるような場所。


ここは金山悦延さん、通称「サブさん」の工房です。青いツナギ姿で川べりに立つ人影があれば「ああ、サブさん今日はあそこにおるわ」と言われるような、この村の名物おやじ的存在の一人。
土木のお仕事の合間、少しでも時間があれば、川にいるかここで何か作っているというサブさん。手作りのルアーは、元々自分の道具として独学で作りはじめたものだったとか。

サブさん:ルアーの前はタバコのパイプとか、貝殻のあわびあるやんか。あれでスプーンルアー作りよったんよ。それで昭和52年かな、坂本ダムにフランスから輸入したブラウン(トラウト)が放流されて、それ釣るのに作り出したんがはじまり。自分でつくるのは、お金がないから(笑)。素材はそこらじゅうにあるよって。

サブさんのユーモアに溢れた人柄に加え、大好きな釣りや魚の話題とあって、気づけばこれまでにないほど雄弁な周蔵さん。サブさんの「ルアー作りワークショップ」のチラシを見て以前から興味を持っていたというみさきさんも、「作りたい!自分の作ったルアーで釣るって、楽しいでしょうね」と次回の機会を心待ちにしている様子でした。

サブさん:釣り好きなんやったら、ここ来たら楽しいで~。来てくれたらうれしいけど、買い物とか、不便は不便やで。ただ空き時間がいっぱいあるよって。なんか趣味あったら、いいとこやね。
と、正直な言葉をかけてくれたサブさんに別れ際、「いつ釣りにくるのがいいですか?」と次回来訪の約束も取り付けた周蔵さん。守崎夫妻にとってまた一人、会いに来たい人が増えた、午後のひとときでした。

心地よい疲れと楽しい思い出でいっぱいになった頭と身体を休めるため、夜の交流会までの間は一時休息の時間に。それぞれ拠点に戻り、しばし過ごします。

日も落ちあたりがすっかり夕闇に包まれた頃。小谷さんが女将を務める「民宿100年」では、守崎夫妻を歓迎する交流会の準備が整っていました。

宴の肴は、アマゴの唐揚げ、アマゴのアクアパッツァにおでん。

そのほか、鹿肉のロースト、鹿肉のパテとバゲット、鹿ひき肉入りのキンパと「鹿肉づくしメニュー」が並び、その準備には前回の「暮らす奥大和」をきっかけに移住した猟師・渡部智大さんも手を貸してくれたとのこと。

そんな、手間暇と心が込められた料理の数々を囲み、たくさんの方たちが集まってくれていました。スタッフまで含めれば総勢19名という、この小さな村ではなかなかの大宴会のはじまりです。

地域内外、職業も様々、世代も全くばらばらな人々。よく見知る人も初めての人も関係なく、隣り合う者同士自己紹介がてら語らい始めたり、向かい合う数人で盛り上がったり……。広い座敷の中にいくつもの人の輪が生じては広がり、縮み、また新しい輪ができては刻々と移り変わっていきます。
初めはやや緊張気味だった守崎夫妻もいつしかそれぞれに別の輪の中で、個性あふれる上北山の先輩たちとの会話に興じていました。


多様で素朴で賑やかな、まるで上北山村そのもののような交流会の光景を眺めながら、ホストの二人に、活動において「大切にしていること」を訊いてみました。

小谷さん:移住っていうことで言ったら、無理なくというか。「いいんじゃない!?こっち来たら?」とかは絶対に言いたくなくて。
久米さん:そうそう。最初は入り口として私たちが関わったけれど、その人が何回か来ているうちに別のつながりができていって。「あの人と友達になったらしい」とか「こっち住むことになったんだ」、みたいな感じがいいよね。
小谷さん:それがベストだね! 私たちがやりたいのは、あくまできっかけづくり。この人と友達になりそうとか、そういうのはもちろん感じることもあるけど、それって絶対じゃない。私たちだけの考えではわからない相性ってあると思うから。だけど入り口は絶対に必要だと思うから、その入り口になりたいだけ。それ以上に関わってやろうなんて、全然思ってないのよ。

小谷さん:私も含めて、みんなが楽しいって気持ちが一番大事。今だってすごい楽しいし、それでやってるだけで、移住促進しないといけないから、とかではない。だから来る人たちにも無理強いはしないし、無理やり来てもらったとしても、多分良い結果にはならないし。「こんな所ですよ、よかったらどうですか?」くらいの気持ちで。自分自身が楽しみを創り出す人、自分が楽しく暮らせるのがここやなって思う人が増えてほしい。それでここにいる人たちみたいに、それぞれの思いがあって頑張ってる人が増えていけばいいんかなって思ってて。
久米さん:そうだね。やっぱり都会で働いていると、自分はこの仕事をやりつづけなきゃいけないって、そこにしか道がないと思って生きてる場合も多いけど、せっかくこういうところに来るから、興味があることをつなげて暮らしてる、みたいなのが一番いいかたちだし、そういう人が増えることが結果、地域のみんなにとっても楽しい地域につながっていく。上北山みたいな地域だと、結局みんなそれぞれ役割みたいなのがあって、それを日々果たしながら自分が地域の一員になってるっていう、この感覚はやっぱり安心感というか、なんかお金だけじゃない価値を感じられるスケール感なのかもしれないね。
二人の言葉の中には、「一言に“地域”といっても突き詰めれば、人と人。だからこそ、それぞれの存在を尊重したい」という信念を感じます。

人と人が出会い、語り合うところに温もりが生まれる。それが本当は「地域」と呼ばれるものなのかもしれない。そんなことを思いながら、おいしい料理とお酒、何にも代えがたい人の温もりに皆酔いしれながら、二日目の夜は更けていきました。

雨上がり。しっとりとした少し冷たい空気が心地よい、最終日の朝です。

ここまで本当に濃密だった2日間。残り時間はゆったり過ごすことになりました。

移住体験住宅の利用手続きのため村役場に立ち寄った後(ここでも中本さんのベンチを発見!)、少し車を走らせ訪れたのは河合地区にある倉庫のような建物でした。道路沿いに所狭しと並ぶオブジェのような作品たち。ここは、2年前の「暮らす奥大和」でもお邪魔した小松広一さんのアトリエです。

家業の林業をはじめ、板前など様々な経験をしてこられた広一さん。今は村議会議員や消防団長などを務めるかたわら、「ここでこうして遊んでるんです」とにっこり。

川原やダムで流木を見つけてきては、ここで時間をかけて作品にする日々を楽しんでいるのだそう。準備してくださっていた焼き芋とお茶をいただきながら、制作や木のことだけでなく、50年以上続けている釣りや魚突きのあれこれ、魚の捌き方、ちょっとやんちゃだった若かりし日の思い出まで、たくさんのお話を伺います。


続いて案内された小松さんの「スタジオH.E.N」は、さらに圧巻でした。



テーマパークのようなゲートをくぐると、イベント広場のようなスペースが。

大きな薪ストーブに三連の囲炉裏の座席があり、民族資料館のように、山仕事や筏流しの道具が飾られたコーナーまであります。


鉄骨の溶接から、3年以上の月日をかけて全て一人で作り上げたというこの場所。現代アートの大先生の「芸術はナントカだ!」という名言を体現するように、小松さんの個性が爆発していました。

奥のステージにはカラオケも設置され、村のみんなで集まりカラオケ大会を催したりすることもあるそうです。

小松さんやサブさんのように、遊びに全身全霊を傾ける大人たちがいて、こんな「変」な場所がある地域は、きっと楽しいところに違いありません。
広一さんに別れを告げた後は、役場の北岡さんが合流。内覧可能ないくつかの村営住宅を見せていただきます。

多くの移住組も住む団地。見晴らしの良い2階のい窓が印象的な高台の物件。それぞれの長所と短所を確かめつつ、もしここで暮らしたら……とイメージを膨らませる二人。

さらに、移住4年目の西田智子さんのご自宅も見せていただけることになりました。

智子さんは、関東から移住後しばらくして、小谷さんに紹介してもらったこのお家に一目惚れ。二つ返事で入居を決めたといいます。日当たりの少なさや吹き込むすきま風などと戦いながらも、そのデメリットを上回る住み心地の良さがあるのだそう。

智子さん:朝起きて外を見たときに緑が飛び込んでくる。こういう暮らしを知ってしまうと、もう離れられないよね。
お部屋いっぱいに智子さんの好きが詰まった、智子ワールドとでもいうような素敵な空間には、自分が本当に好きな場所に住めることの幸せがたっぷりと感じられました。移住したきっかけや上北山村の人の良さ、アドバイスなども伺った後は、最後の目的地である「木和田テラス」へと向かいます。

道中、梅屋商店の駐車場に、元地域おこし協力隊の塚原浩一さんのキッチンカーが出店していました。

曜日ごとに村内各所に移動して販売されているお弁当。「毎週違うメニューを」というこだわりのおかずに、山盛りのごはん、そして500円という驚くほど良心的な価格。

このお弁当を楽しみにしている村民が多いというのも納得です。この日も地元の方たちで賑わっていましたが、私たちもなんとかゲット。

小橡川上流、美しい清流のほとりにある小谷さんと久米さんの活動拠点「木和田テラス」に到着しました。川沿いの廃屋を自分たちでリノベーションしながら、イベントなどを通じて人が集う場所、上北山を感じてもらう場所として活用しているこの施設。澄んだ空気、おだやかな川のせせらぎに耳を傾けながらお弁当をいただきます。

食後は、久米さんが二人に合いそうな上北山村の求人情報をまとめて案内してくれました。ホテルスタッフ、学童指導員や養護教諭といった教育関係、給食や柿の葉寿司の調理員、福祉関係のお仕事と、今募集されている分だけでも想像以上に様々な職種がありました。
そこに「コーヒー入りましたよ」と声をかけてくれたのは、この取材にカメラマンとして同行してくれている村上由希映さんの夫・村上弘好さんです。弘好さんに促され、木和田テラスのお隣に立つ、こぢんまりとした建物へお邪魔します。

借りた時にはぼろぼろだったこの家を3年ほどかけて、仕事が休みの時間に滞在しながらリノベーションしていった弘好さん。そうして、今はほぼできあがった建物内には、広々とした板張りの空間に薪ストーブ、新調されたキッチン、バックヤードにはバスユニットまでありました。たった一人でここまでの改修を行った技術の凄さはもちろんのこと、これらの材料のほとんどが、解体業に携わる弘好さんが現場から持ち帰った廃材だというのだから、驚きです。
弘好さん:極力お金をかけずに、捨てるもんを利用するような。それがほんまのSDGsちゃうかな、って思うんよね。

ほとんど倒れかけていた板戸はまっさらなガラス張りになり、差し込む光が明るさと温もりを満たす空間。そこで、由希映さんが自家焙煎したコーヒーを淹れてくれました。
由希映さん:そう、カフェしたいなーって思ってて。私が来れる時だけなんで、ほんま一年に数日しか開けられませんけど(笑)。
一年に数日しか開かない、大台ヶ原からいちばん近いカフェ。それはそれは、噂を呼ぶお店になりそうです。
ほっこりと寛ぐ時間を過ごすほどに、終わりの時は近づいてきます。最後に、守崎夫妻にそれぞれ、この3日間を振り返っていただきました。
まずはみさきさんから。

みさきさん:上北山の自然の素晴らしさは十分に分かっていたんですけど、今回参加させていただいて、こんなに村の人たちと関われて、どんな人が住んでて、どんな仕事をされているのかっていうのを知ることができて、すごくいい経験になったと思っています。何よりも人が。そう、人情深いっていうのと、やっぱりみなさん個性的な人が多かったっていうのが印象的で。なかなか昨日みたいなご飯会とか絶対体験できないなって。大きかったなって思います。
木工とか木造とかも本当に好きなので、今回いろいろ回ってお話を聞けて、やってみたいな、関わりたいなって気持ちがよりいっそう強くなりました。ゆくゆくは自然のあるところに移住したいと思っているので、すごく今後の参考になる貴重な3日間でした。ありがとうございました。

つづいて周蔵さんです。
周蔵さん:自分は、「好きなことを生業にするな」と言われて育ってきた人間で。今もサラリーマンとして働いているんですけど、この3日間過ごしてきて、生業ってそれ一本で食える食えないは別にして、楽しいと思うことを仕事にできるんやなって思うようになりました。やっぱり、その考えが180度変わったっていうのが一番ですね。
あとは、僕たち二人ともちょっと人見知りで、妻が人見知りやったら僕はその10倍人見知り(笑)。波長の合う人と話して、スイッチが入ったらようやく心が開けるっていうところがあるんですが、今回さまざまな方にお話を伺う中で、荒療治といいますか、郷に入れば郷に従えじゃないですが、こういうコミュニティに入ったらそういうのも改善されていくんちゃうかなって感覚もありました。非常に刺激を受けることができました、ありがとうございました。
小谷さんからも。
小谷さん:がらっと変わったんやね!仕事に対する価値感って、けっこう重要なもの。「ああ、こういう考えでもいいんや」って思えるようになったら、今後の生き方っていうのも変わってくるかもしれないね。私たちはもちろん二人がこの村を選んでくれたら嬉しいけど、まずはお二人のこれからにとっての起爆剤のような、何かきっかけになったらいいなと思っていたので、今の感想はすごく嬉しいです。我々もこの企画のおかげで、逆にいろいろ知ることができたところもあって、めちゃくちゃ楽しませてもらいました。案内しながら結果、こちら側も新たな上北山を知った、たくさんの新しい出会いがあった3日間でした。今回は参加してくれて、この村に来てくれて、ありがとう。
最後に久米さんから。
久米さん:私もここに暮らすようになって、地域の人たちといろんな場面で一緒になることで、お仕事してる姿と日常の姿、いろんな角度からその人の魅力が見えてくるっていう人との関わり方が面白いと思っていて。二人にも「魅力的な人いっぱいいるな」「ああ、この人面白い」と思ってもらえて、すごく嬉しいです。そういう親戚みたいな家族のような、お付き合いできる人がたくさんいるっていうのは、こういう地域独特のものなのかなって思ってて。もちろん人それぞれ良いところ悪いところはあるけど、なんかそういうのもひっくるめて「面白いね」って思う。今回、二人も自然に、この地域の人たちに馴染んでいる感じがあって嬉しかった。中本さんのお父さんが「前もあったことあるかなあ?あのふたり」って、なんか初めてあった気がしないみたいに言ってて。「ぜひ来てくれたら嬉しい」って言ってらっしゃいましたよ。
「人見知り」という一見、田舎暮らしのイメージには不似合いの二人が、たくさんの見知らぬ人々に会いに行き、たくさんの言葉を交わした濃厚な3日間がこうして幕を閉じました。きっと、私たちが想像する以上に、二人には大変な思いもあったかもしれません。しかし、朝の釣りや地域の方との語らいの場面で「本当に人見知りなのか?」「実は上北山にぴったりの夫婦なのでは?」、そのように感じてしまう瞬間にも数多く出会いました。
もちろん実際の「移住」とは、そう単純なものではないでしょう。二人が理想とする暮らしに辿り着くには、まだまだ時間がかかるのかもしれません。しかし、少なくとも二人は確かに、その大きな一歩目を踏み出したローカルステイだったように思います。

この3日間を終えた二人には今、家族でもなく親戚でもなく、でも他人でもないつながりを感じられる人々がこの上北山にいます。地域との関わり方も、すぐに移住することそれ一本ではなく、それぞれの形があるはず。次は村上夫妻のように、自分たちらしい地域との関わり方について考えてみるのも面白いかもしれません。
山の雪も融け、暖かくなる頃。きっと上北山のどこかの川原で、遡上してくる若魚たちと共に、帰ってきた二人の姿を見ることができるでしょう。きっと、そんな気がしています。ご紹介したい出来事ばかりで、思いがけぬ長文となってしまいました。最後までお読みいただいたあなたに感謝を。
事例に戻る