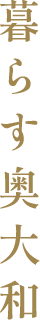 Try Living in Okuyamato.
Try Living in Okuyamato.
Organized by Nara Pref.
Organized by Nara Pref.
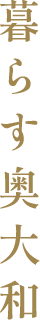

文=大窪宏美(equbo*) 写真=都甲ユウタ
2024年12月22日。クリスマスを目前に控え、天川村ははらはらと舞い落ちる雪で白く霞んでいました。

近畿最高峰の「八経ヶ岳」を擁し、村全域がユネスコエコパークに認定されているこの村。「天川ブルー」と称される美しい渓谷や情緒溢れる温泉街など観光資源も豊富で、広い世代の人々を魅了してやまない行楽地として知られています。
そんな天川村で初めての「暮らす奥大和」、そのプログラム初日。うっすらと覆われた道に轍をつけて到着したのは、京都市内で喫茶 「暖々(だんだん)」を営む渡邊健吾さんと斎藤萌香さんです。現在移住先を検討中の二人は知人を介してプログラムの募集を知り、この日初めて天川村にやってきました。

健吾さん:こんにちは。寒いですね~!
挨拶を交わす間にも、肩や髪に雪が積もります。移動の疲れを癒し暖を取るため、まずはホスト役である畠中さんのご自宅で一息つくことに。

駐車場まで出迎えてくれた夫・利治さんの案内で中に入ると、妻・亜弥子さんと2歳になったばかりの長男・清史郎くんがニコニコと歓迎してくれました。

昨年購入されたばかりという民家は、元々画家兼デザイナーの方の家だったそう。あちらこちらに面白くて素敵なものたちが散りばめられています。

ホストファミリーの亜弥子さんと利治さんは、それぞれ国内外で経験を積んだ料理人夫婦。若くしてフランスの二つ星レストランのスーシェフとして活躍したり、和食料理店で店長を担ったりと、それぞれに錚々たる経歴を持ちながらもあたたかな人柄が親しみやすい、気さくでチャーミングなお二人です。


出産を機に亜弥子さんの地元である天川村に移り住み、夫婦で自然派ジェラートのお店「TENKARA GELATO」を創業。2025年には完全予約制のレストラン「SEN」をオープンするなど、食を通して天川村を盛り上げる活動にも取り組んでおられます。
一方参加者の健吾さんは、珈琲焙煎師でありながら和太鼓パフォーマーとしても活動中という珍しい経歴の持ち主。

プロの太鼓芸能集団に在籍した後、新たな表現方法としてコーヒーの道へ。地元新潟のコーヒー会社や京都のカフェで経験を積んで独立し、現在は「KENGO COFFEE」を展開しています。

パートナーの萌香さんは、栄養士の資格を持つパティシエ。東京のカフェで製菓部門を任されていましたが、COVID-19の流行を期に地元新潟にUターン。「つぼみ」という屋号で季節に寄り添う菓子作りをするなかで健吾さんと出会い、共に京都市内に移住して、2023年から二人で店舗を間借りして喫茶「暖々」を営業しています。
京都での生活は充実しているものの、自分たちが求める暮らし方や表現していきたいことはもっと自然に近い環境にあるのではないかと感じ、移住を検討しているというお二人。
この日が初対面となる四人ですが、まずはこたつを囲んで改めて自己紹介。畠中夫妻が、簡単に地域のあらましや見どころなどを教えてくれます。

ひと休みしたら、早速亜弥子さんのお父さんにお話を伺うため、「せせらぎの宿 弥仙館」へ。

弥仙館内でオープンを控えたレストラン「SEN」に特別に入らせてもらい、そこで畠中稔さんにお話を伺いました。

宿を営む傍ら、村について見分を広めるゆるくて楽しいコミュニティ「てんかわ研究所」を運営する稔さんは、村のことなら何を聞いても答えが返ってくる天川愛溢れる方です。

稔さん:何から話そうか。こんな山ん中やけどすごい歴史が古くて、話せば長くなるんやけど…
修験道の聖地である霊峰・大峯山のこと、夏には連日大渋滞するほど多くの人を魅了する美しい川や森のこと、村の中央に鎮座する天河辨財天社の節分祭では、前夜に鬼を迎える儀式が行われること……歴史・自然・文化など語りつくせない魅力に満ちたこの土地について、稔さんはひとつひとつ説明してくださいます。

「移住するなら歴史や伝統、地域のお祭りが残っているところがいい」と考える健吾さんと萌香さんは、質問を交えながら興味深そうに聞き入っていました。

稔さん:この村の冬は寒さが厳しい。柑橘類とか、寒すぎて育たない作物もあるから、畑をしたいと思ってるならよく考えやなあかん。その代わり白菜なんかはトロットロでめちゃくちゃおいしいで。スーパーなんかに売ってるのと全然違う。テレビやネットで「田舎はプライバシーが守られない」なんて言われたりするけど、それもどう捉えるかやな。人口が少ない分みんなが顔見知りで、道を走っているだけであの車は誰のやとか、いつどこで何をしてたかなんて、意識してなくても見えてしまう。行事で集まる機会も多いし、都会と違って勝手に付き合いが深くなるのはしょうがない。
この村の良いところも、ネックになる可能性がある事柄も、包み隠さず話してくださる稔さん。

稔さん:その地域のブランドやイメージで決めんと、自分たちの趣味・生き方に合った場所を選ぶのが大事やと思うわ。移住してきてもすぐに出て行ってしまう人も多い。「寒さが厳しい」と思うか、「雪景色が美しい」と感じるか。街とは違う田舎ならではの密な関わり合いがあることを「楽しみ」と思うか、「煩わしい慣習」と捉えるか。まあまあ、巡り合わせですから。
観光地として賑わう一方で過疎化が進む現状に、若い人に入ってきてほしいという思いは言うまでもありません。ただ、せっかくなら村の伝統や天川村での生活を好きになって、大切にしてくれる人に住んでほしい。稔さんの言葉からは、二人の未来を応援する気持ちと共に、故郷への深い愛情が伝わってきます。
萌香さん:村全体が大家族みたいですね。
健吾さん:僕らはそういうのは大切なことだと思ってます。

一通りお話を伺った後は、利治さんの提案で、稔さんも一緒に天河大辨財天社を参拝することに。


日本三大弁財天の筆頭とされ、芸能の神様として知られるこの古社は、これまでにも映像作品の撮影地になったり、音楽や漫才が奉納されたりと、国内外から芸能に携わる人々の祈りが寄せられてきました。観光はオフシーズンとなるこの時期でも、全国各地から参拝者が絶えません。

参拝の作法について教わりながら、御手水で身を清めます。鳥居をくぐって階段を上がると、拝殿の左奥に本殿、向かい合うように能舞台が現れました。

本殿に向かう祭壇の前にかけられた本坪鈴は、神宝である「五十鈴」を模した独特の形状をしています。総重量は30キロにもなるというだけあって鈴尾綱はずっしりと重く、大人の力でもやっと持ち上がるかどうかというぐらいです。稔さんや利治さんがぐるりと回すと、カランカランという聞きなれた音とは違う、重く奥行きのある和音が響きました。

天川村にはかつて、子どもたちが叩く「弁天太鼓」というものがあったそうですが、子どもが減ってなくなってしまったそう。
稔さん:立派な太鼓はあるねんで。教えたってよ!
稔さんの言葉に、太鼓奏者の健吾さんは「そういうのを復活させる活動をしたいです」と目を輝かせていました。

続いて、境内にある役行者堂や塔頭寺院のひとつである来迎院も案内していただきます。

そこには、弘法大師・空海が手植えしたと伝わる樹齢1200年の大イチョウがそびえていました。

悠々と伸びた枝には毎年実が鈴なりだそうで、地域の人たちは銀杏や落ち葉の掃除に追われて大変なのだそう。と、そうしてる間に、稔さんが宿に戻らなければならない時間になりました。
稔さん:色々説明したけど、言葉よりも感じてください。焦らんと、自分がどう生きていきたいんか。家も人も、ご縁があるかどうかやな。いいご縁がありますように。

温かな言葉を受け取り、お礼を言って稔さんを見送ります。

次に、村内でパン屋「prana(プラーナ)」を営む永山直津紀さんに会うため車で移動します。お店はすでに営業を終えた時間だったため、ご自宅にお邪魔することに。

こんがりと焼き上がったクラストに美しく開いたクープ。見るからに香ばしいパンたちを用意して、永山さんは迎えてくれました。国産小麦と自家製酵母を天川の水で捏ね上げたパンは、おいしさや安全性はもちろんのこと、環境にも配慮して生み出されています。

萌香さん:わあ、おいしそう~!
「移住はしまくってここに来たから、なんでも聞いてください」と、永山さん。村での暮らしのこと、家探しのこと、生き方のこと。ご自身の経験をもとに、明るく飾らない言葉で話してくださいます。
永山さん:空き家の情報はないように思えても、とりあえず住んじゃえば入ってくるよ。ご縁づくりは日々の暮らしでしかないからさ。

それぞれの得意を活かして喫茶「暖々」を営む二人に、「それならどこに行っても生きていけるね」とエールを送ってくれました。

永山さんに別れを告げ、続いて畠中夫妻が営む「TENKARA GELATO」に立ち寄ります。

利治さん:寒いですけど、よかったら食べていってください。

選び抜かれた素材と利治さんの感性から生み出されるフレーバーは、どれもこれも興味をそそられるものばかり。二人は迷いながらも「甘酒シナモン生姜」と「キャラメルスイートポテト」に決めました。



健吾さん:めっちゃおいしい!
口の中で甘くとろけるジェラートに、笑みがこぼれます。繊細な風味を堪能しながらお店作りや食材などについて話を聞き、畠中夫妻の地域に根付いた活動に触れて、「仕事もその地域での暮らしの一環としてやっていくのはいいな~」と、移住後の生活に思いを馳せていました。
お店を後にし、「天の川温泉センター 木々の湯」で温もった後は、畠中家で夕食をいただきます。この日は移住者である成尾亮太郎さんと山本晋也さんを招いてのホームパーティーです。キッチンに立ち、手際よく調理を進める畠中夫妻の様子は、さながらレストランの厨房のよう。



おいしそうな香りを漂わせて、できたての料理が次々に運ばれてきます。

春菊と人参の春巻き、蕪と葱のソテー、大根と柿のなます、じゅわっとバターが絡んだ肉厚な焼き椎茸。どれもシンプルな料理ですが、旬の食材の持ち味が生きる組み合わせや絶妙な火の入り具合に、プロの技を感じます。

村での暮らしやこれから挑戦していきたいことなど、会話が盛り上がる間に、メイン料理の猪肉のローストが登場しました。

萌香さん:びっくりするぐらいおいしい! 嫌な臭みとか全然ないですね。
猪肉はこれまでほとんど食べる機会がなかったという萌香さんは、その味わいに感激した様子です。このお肉は、元々は京都の日本料理店の料理人だった山本さんが猟で獲ったもの。料理の知識や経験を活かして丁寧に処理された猪肉は、ジビエ特有のクセが少なく、旨味がしっかりと感じられます。ゆくゆくは狩猟にも挑戦し、獲物の皮を使って自作の太鼓を作ってみたいという健吾さんは、山本さんに熱心に質問を投げかけていました。

成尾さん:この家でご飯を食べると、いつも困っちゃうんですよね。おいしくて嬉しいから…こんなご馳走、逆にどうやってお返ししようかって。
草刈りをしたり、山菜を採ってきたりしてお礼をするという成尾さんのお話から、金銭を介さなくても成り立つ健やかな循環が見えてきます。都会に比べるとお店やサービスの選択肢が少ないこの土地で、それぞれが持っているもの、知識・技術を提供し合うことは、暮らしをより豊かで快適なものにしてくれるようです。

お酒も進み、締めのビリヤニに舌鼓を打ち、会話もますます盛り上がって、楽しい夜が更けていきます。


話はまだまだ尽きませんが、明日を見据えてお開きとなりました。

二日目の朝。

この日は天河大辨財天社で行われる「朝拝」に参加。凍てついた雪道を踏むと、静かな参道にシャリシャリと心地よい音が響きます。

神仏習合の習いが残るこの神社の朝拝では、「大祓詞(おおはらえのことば)」についで「真言」も奏上されます。宮司の伸びやかな声と、笛や太鼓の音。呼応するように葉音や鳥たちの声も重なり、自然と人の営みが一体となるひとときは、天川の暮らしのあり方が表れているようにも感じられます。

参拝を終えてお神酒で身を清め、清々しい表情の二人が吐く息は、朝の清澄な空気にくっきりと白く浮かんでいました。

帰宅すると、畠中夫妻が朝ごはんを用意して待ってくれていました。



炊きたての土鍋ご飯に具だくさんの豚汁、お漬物の盛り合わせの中には自家製のからすみも並びます。

優しい味にほっと温まり、畠中家の愛猫「カツオ」と「サバ」を愛で、保育園の登園時間になった清史郎くんを皆で見送ってから出発です。

この日は空き家を案内してもらうため、10時に村役場職員の奥田さん・石原さんと待ち合わせ。「TENKARA GERATO」のスタッフであり、ご自身も物件探し中という野口史枝さんも一緒です。

天川村は西部・中央・洞川の三つのエリアに分かれます。まず向かったのは西部の和田地区にある県道沿いの一軒家。

空き家バンクにも出ている物件で、村の制度で改修補助もあるということでしたが、畑付きの店舗兼住居を探している二人にとっては少し手狭だったようです。
次に訪れたのは栃尾地区。空き家になる前は地域おこし協力隊の方が住んでいたそうで、建具を取り払った広々とした平屋に、所々青や緑の色ガラスをはめ込んだ障子戸からたっぷりの自然光が入り、とても明るい印象です。


可愛らしいタイル張りのキッチンも好印象で店舗向きの物件のようではありますが、畑や駐車場になるようなスペースがなく、やはり少し手狭な印象でした。
続いて案内してもらったのは、中央エリアの北小原地区にある山と畑付きのお家です。ここは最近、すでに入居が決まってしまったそうですが、二人の希望に近い条件だったため、参考までにと見学させてもらうことに。「こういう家をなるべく自分たちで直して住めたらいいよね」と、会話も弾みます。
最後に、村役場からもほど近い中越地区にある賃貸物件にやってきました。

萌香さん:わぁ、かわいい!
昔ながらの土壁に型板ガラスの木製建具がはめ込まれたその家を、二人は一目で気に入った様子です。ここは最近空き家になったばかりということで、比較的状態が良く、すぐにでも住めそうな印象。日当たりも良好で、家の前には庭や畑も付いています。
こっちは生活スペースや宿にして、離れの納屋は喫茶やギャラリーに……と、二人のイメージも膨らんだようですが、内見はひとまずここまで。

一旦役場に戻り、奥田さんから建設中という定住促進住宅の説明を聞いた後、村で人気の「かどや食堂」で昼食をとることになりました。
明るくにこやかなご主人に案内されて小上がり席につくと、開けた厨房からお出汁のいい香りが漂ってきます。健吾さんはカレーうどん、萌香さんは玉子うどんをチョイス。

亜弥子さんおすすめの巻きずしは、みんなで分け合っていただきました。

熱々のおうどんに、身も心も温まりました。

畠中家に戻ると、健吾さんが焙煎した豆で食後のコーヒーを淹れてくれることに。
用意してくれたのは「KENGO COFFEE」の定番で、二人のお店の店名を冠した「暖々ブレンド」。ブラジル・インドネシア・バリの3種類をバランスよく調合した中深煎りの豆は、ブラックはもちろん、ミルクと組み合わせてもおいしくいただけるオールマイティーなブレンドです。豆の組み合わせ、焙煎方法、抽出の時間や温度など、準備を進めながら健吾さんと利治さんのコーヒー談義に花が咲きます。

利治さん:コーヒー、深いっすね。
健吾さん:やりだしたら絶対ハマりますよ。
食に携わる者同士、キッチンで盛り上がる二人はとても楽しそうです。大峯山脈から水を引いている天川村の水道水のおいしさに感激していた健吾さんは、「ここの水で淹れるとどんな感じになるのか楽しみだな」と、ワクワクした表情で挽きたての豆にそっとお湯を落としました。

ふわりと甘くほろ苦い湯気をたてて抽出されていくコーヒー。健吾さんの丁寧な所作ひとつひとつを、利治さんがじっと見つめます。

できあがったコーヒーが畠中家愛用のカップに注がれ、こたつを囲んでお茶の時間になりました。

亜弥子さん:あ~いい匂い。やっぱり一日一杯はおいしいコーヒーがある生活がいいな。
萌香さん:すっごい味がまるい! 京都の水で淹れるのと全然違う。やわらかくて、このブレンドこんなだったっけって思うぐらい違いますね。
天川の水でまろやかに抽出されたコーヒーを皆で楽しみ、ゆっくりと休憩した後は、洞川エリアへ向かいます。

洞川は修験道の聖地・大峯山の登山基地として古くから栄えてきた地域。標高約820mという高地に位置することから村の中でもひときわ雪深く、また旅館や商店が軒を連ねる、雰囲気たっぷりの温泉街。この町並みの奥に、日本百名水にも選ばれている湧き水「ごろごろ水」の採水場があります。
だんだんと深くなる雪道を慎重に進み、まずは大峯山の登山口を訪れます。


今も女人禁制の山とされていますが、元々は女性が危険な目に合わないように、という思いやりの心から始まったものだそうです」と、昨日弥山館の稔さんが教えてくれたのが思い出されます。

しばらく見学した後、少し下って「ごろごろ茶屋」へ。ここでは名水「ごろごろ水」を使ったコーヒーやわらびもちなどのメニューが楽しめるほか、採水場で水を汲むことができます(有料)。購入したタンクいっぱいに汲んで、その場でひとくち。

健吾さん:あー、うまいっすね。この水でコーヒー淹れるの楽しみだな。
二人は天川村の水にすっかり魅了されたようでした。再び車に乗り込み、大峯山頂にある大峯山寺の護持院のひとつ「大峯山龍泉寺」を訪れます。



利治さんのガイドを聞きながらお参りし、境内にある「重軽石」にチャレンジしたり、修験者が水行や瀧行を行う行場を見学したり。



そのまま少し周囲を散策した後、春にオープンしたばかりという「洞川温泉ビジターセンター」で温泉を満喫しました。
すっかり温まった体で畠中家に戻ると、一足先に戻った利治さんと亜弥子さんは、夜の懇親会に持ち寄る料理を準備して待ってくれていました。

キッチンからはじゃがいものガレットや、北海道から届いたというエゾ鹿の焼けるいい香りが漂ってきます。

亜弥子さん:おにぎり、一緒ににぎってもらっていいですか?

ふっくらと炊きあがったむかごご飯の鍋を囲み、皆でわいわいと作業すれば、あっという間にかわいい三角おにぎりが大皿いっぱいにできあがりました。

畠中夫妻が準備してくれた料理の数々を手分けして持ち、懇親会会場となる高木家にお邪魔します。そこでは今夜のメンバーがすでに揃って準備をしてくれていました。

キッチンは調理とおしゃべりで盛り上がり、居間では子どもたちが仲睦まじく戯れ合っています。

「水がいいところに住みたい」と、あちこち探して天川村にたどり着いた高木さん一家は、移住10年目。この家の生活用水が井戸水と山水だったことが決め手となって、京都から引っ越してきたそうです。

希さん:夏はクーラーもいらないし、冬は寒いけど薪ストーブさえあれば大丈夫。生活の質が上がって冬が楽しみになるから、絶対あったほうがいいよ。
健吾さんと萌香さんは、設置方法や薪の調達先などについて興味津々です。
遊びをやめたくない子どもたちをなんとか諭していったんみんなでテーブルを囲み、乾杯。持ち寄った豪華な食事が、それぞれの口にどんどん運ばれます。


家主の高木雅典さんと希さん、陶芸家の渡部彩弥さん、午前中一緒だった野口さんと、皆さん移住してきた方ばかり。天川での暮らしや家探しについてなど、色々お話を伺いました。
2ヵ月程前に大阪から越してきたばかりの渡部さんは、人が優しく、都会よりも安心して暮らせているとのこと。

何か嫌なことがあっても、川に行って流れを眺めていれば不思議とすっきりするのだそう。熊野川最源流域での、美しい水が身近にある暮らしぶりが伝わってきます。

薪ストーブで暖まった室内はぽかぽかと心地よく、この村で暮らす皆さんの生の声を聴きながら、おいしい料理やお酒を囲んで充実した時間が過ぎていきます。

健吾さんと萌香さんが、移住先では喫茶のほかに小さな宿やギャラリーを構想していること、自分なりの小さなお祭りをつくりたいことなど、今後していきたい暮らしや活動について話しをすると、「今ちょうど、いい感じに面白い人が集まってきてるし、来てくれたら楽しみだな」と歓迎の言葉が贈られました。


楽しい夜はあっという間。まだまだ遊び足りない子どもたちのパワーに圧倒されつつ、名残惜しい気持ちを抑えて交流会はお開きに。翌日に備えて2日目も終了となりました。

そしていよいよ、3日目の朝です。

最終日は周辺の散歩から、ゆったりとスタートします。畠中夫妻が用意してくれた朝食のブリトーは、初日に会った永山さんのお店「prana」の酵母グラノーラ入り。


昨日汲んできたごろごろ水で、健吾さんと萌香さんがコーヒーを淹れてくれました。天川村で結ばれたご縁から生まれる、この日だけの特別な朝食セットです。

健吾さん:家の水とごろごろ水で、全然違う!こんな違うんだ。
萌香さん:ここの水の方が柔らかいね。
ごろごろ水の方が少し硬度が高いこと、弱アルカリ性であることなど、色々な要素でコーヒーの味がずいぶんと変わることを実感。水が生活に与える影響の大きさを改めて感じます。

午前10時、畠中家と同じ坪内地区にお住いの井頭東洋さんにお話を伺います。

ご自宅の前で待ち合わせ、「まずは中心に向かいましょう」と、天河大辨財天社を改めて案内していただくことになりました。

ご祭神である辨財天は、古代インドのサラスヴァティー神。現在は芸能の神様としてよく知られていますが、元来水の神様であり、この場所もはるか昔は天ノ川の中にあったそうです。
井頭さん:山で生きる天川村の人々にとって、自然への感謝や敬う心は暮らしの中に根付いている。この神社を大切に思うことは、自然の循環を崇拝するという意味でもあるんです。

言葉のひとつひとつから、この土地で暮らすことへの想いや誇りを感じます。境内をじっくり見学したら、来迎院の大イチョウの木の背部にある船岡山へ。

ここには建御雷神(たけみかずち)が祀られる「船岡神社」があり、古くから信仰される山のひとつですが、他の山々と同じように、戦後に国策の後押しを受けて針葉樹が植林され、その後の林業の衰退により、ほぼ手つかずの放置林となっていました。手入れが行き届かない状態の人工林は暗く、保水力の弱い針葉樹ばかりでは地盤が緩みやすくなってしまいます。

そんな中発生した2011年の紀伊半島大水害では、山腹で深層崩壊が発生し、天ノ川の河道を閉塞。坪内地区の80%が水没し、家屋の浸水や神社の鳥居が流されるなど甚大な被害をもたらしました。氏子の方々は、水神の里で発生した水害に衝撃を受け、このままではいけないと一念発起します。
有志が集まり、井頭さんが代表となって2020年に「天河斎庭」という団体を発足。このあたりの放置林を多様性に富んだ健やかな森へと生まれ変わらせるためのプロジェクトが始動しました。
元来この地にあった自然と共存する暮らしや四季折々の景色を取り戻し、辨財天様を祀るのに相応しい「斎庭(神様をお招きし祀るために祓い清められた聖地)」をつくる。その活動のひとつとして、この船岡山の地権者の方々を説得し、放置されていた針葉樹を伐採して、山から採取し畑で育てた300本以上の広葉樹を植樹したそうです。


井頭さん:もちろん、鹿に新芽を食べられたりもしましたよ。それも想定内です。森の中で野生動物にかなわないのも、当然のことですからね。
明るく見通しが良くなった船岡山の尾根からは、天河大辨財天社を中心とした坪内地区と、奥宮が祀られている弥山も一望できます。


「訪れた人がこの地の素晴らしさを体感し、英気を養ってもらえる場所にしたい」と、今年6月には展望台も設置されました。「杜の舟 宙(SORA)」と名付けられたこの展望台は、水の神様が鎮座する場所にふさわしい舟の形をしています。

井頭さん:ゆくゆくはこの舟で夜空の航海に出られるように、道を整備する予定です。天川の地で見る天の川、降ってくる星屑も掴めるような、素晴らしい体験になると思いますよ。

目を輝かせて今後の展望を語ってくれた井頭さん。その表情からは、「この地を変えていかなければ」という前向きな思いはあっても、様々な課題を目前にした悲壮感のようなものは感じられません。
井頭さん:今は人口が減って年齢のバランスも悪い。バトンを渡せる人もいない状態なんですね。それでも目の前に山積みの課題がある以上、挑戦しないと何も変わらない。一人や二人では夢を形にはできないから、一緒にやっていけたら嬉しいですね。200年、300年と寿命があるといいんですけど、そうはいかないから。若い人にあとは頼んだぞと。

健吾さんと萌香さんは、井頭さんの熱い思いに胸を打たれたようでした。
井頭さんに別れを告げ、この日もかどや食堂で昼食をとりました。畠中家に戻る途中、再びTENKARA GERATOを訪ねると、営業中のお店では野口さんが迎えてくれました。

野口さん:昨日はありがとうございました~! 今日もジェラート食べてもらってって、連絡がありましたよ。好きなの選んでください。

利治さんの計らいで、食後のデザートに再びおいしいジェラートをいただきます。二人は「キウイココナッツ」と「柿ブランデー」を選択。野口さんと言葉を交わし、明るい笑顔に見送られてお店を後にしました。
さて、こうしていよいよプログラムも終わりの時間。それぞれにこの3日間を振り返ってもらいました。

まずは萌香さんから。

萌香さん:楽しくておいしくて、いろんな人の話が聞けて。来てすごいよかったなと思います。この土地が好きで、語れることがいっぱいある人がたくさんいて、それって多分、「ここに住む」って決めて住んでるから話せることだなと。それがこの場所に住むってことなんだなって、わかったような気がする。
やっぱり都会より、こういう自然が近い場所に住んで、やりたいことがいっぱいあるなって改めて思ったような気がします。キャラが濃くて面白い人がいっぱいでした(笑)。
続いて健吾さん。

健吾さん:やっぱり、来ないと感じなかったことが、いっぱいあったなって思います。今は色々ありすぎて、まだ整理できてないんですけど……。井頭さんの「あとは任せた」っていう言葉を聞いて、他人事じゃないなって。こういう想いで良くしていこうと思ってるんだっていうのも、空き家バンクを見てるだけじゃ全くわからなかった。住んでみないとわからないことだったと思います。
今回3日間だけでしたけど、こうやっていろんな人に紹介してもらったことで、本当にいろんなことが知れたし、多分ただ何も知らずに住む以上に濃密な時間だったかなと思います。移住するのであれば、自分たちのやりたいこともそうですけど、その土地で周りの人たちが求めていることも知ってから移住したい。そうしたら、自分たちもより一層、その土地に来てよかったなって思える生活がしていけるかなって。
続いて利治さん。

利治さん:お疲れさまでした。天川村を楽しんでもらえたら嬉しいなっていうのが一番大事だったので、楽しんでいただけていたら嬉しいです。僕らも話を聞かないとわからないこともあったので、知らないことがクリアになった部分がありました。自分たちの役割や、今後必ずまわってくるものがあるので、その時にどう応えるかとか、何ができるのかなっていうのを考えるいいきっかけができたなと思います。
最後に亜弥子さんです。

亜弥子さん:すごい楽しかったです。うちは普段から人を招き入れることが多くて、夏場なんか1ヵ月ぐらい人がいたりとか、出たり入ったりして民宿状態なんです。だから、これまでにもいろんな人を案内してきたけど、がっつり天川の人の話を聞いたりするのは、ただ人が来るだけではやっぱりできないので。こういう機会をもらって自分もすごい勉強になって、私自身が楽しませてもらいました。
今後、天川に住む住まないは関係なく、こうやって縁があって来てもらえたので、天川との関係はできたかなと思っていて。これからどこに住むにしても、ちょっと遊びに行こうかなって来てもらえたり、何かの活動だけに参加するようなかたちで関わってもらえたり、そういう親戚みたいな付き合いとかでもできれば嬉しいです。
多分お二人のお人柄もあって、会う人会う人が「来ちゃいなよ」って言ってて……私も想定してなかったぐらいウェルカムで。みんな誰でも来てほしいわけではないので、多分相性がよかったのかなって。また来てください(笑)。


こうして、四人は笑顔で挨拶を交わし、健吾さんと萌香さんは畠中家を後にしました。

これからのことはわかりませんが、亜弥子さんの言葉にあったように、関係は確かに結ばれたと感じる3日間となりました。この村の清流が様々な地域を経て海に流れ着くように、たくさんの出会いを繰り返し、豊かな関係を結びながら、健吾さんと萌香さん、お二人にとって心地よい暮らしを育める場所へとたどり着けますように。そう願って今回のレポートを終わりたいと思います。
事例に戻る